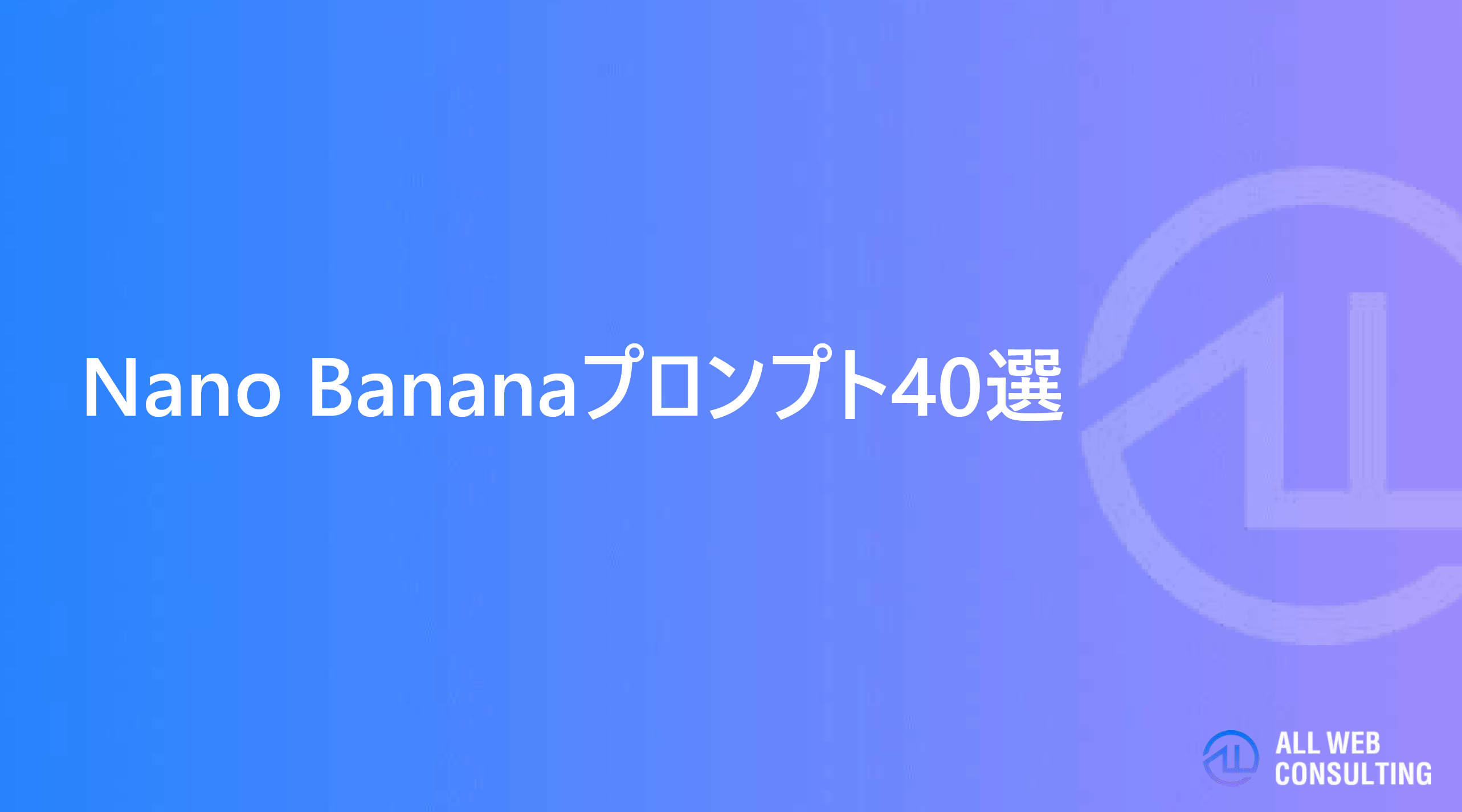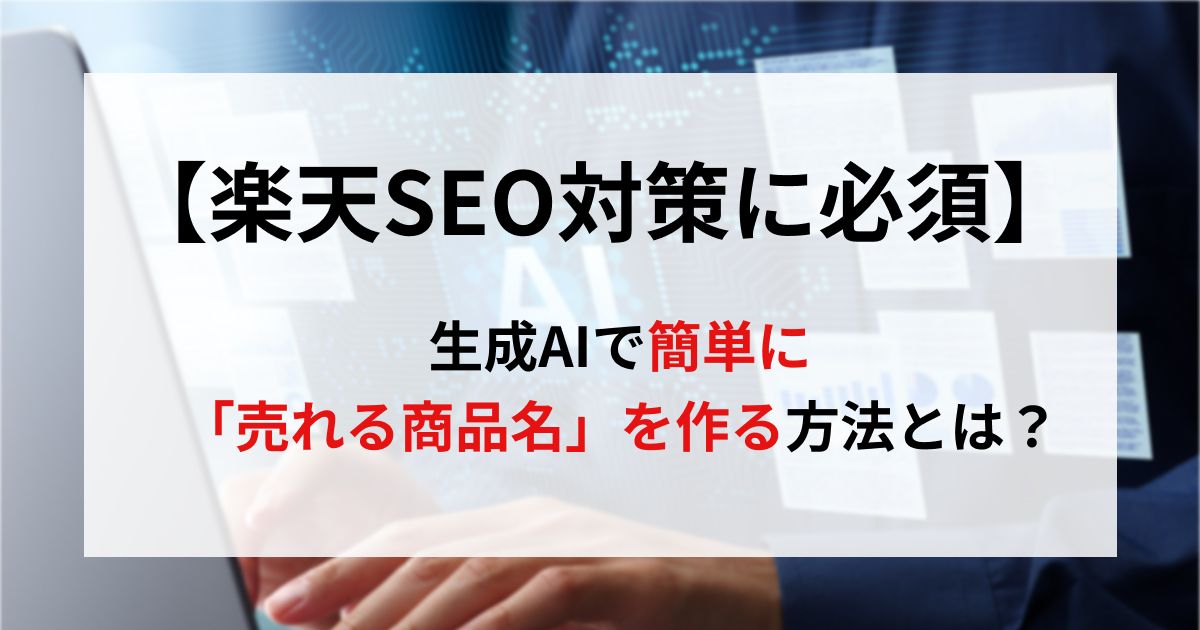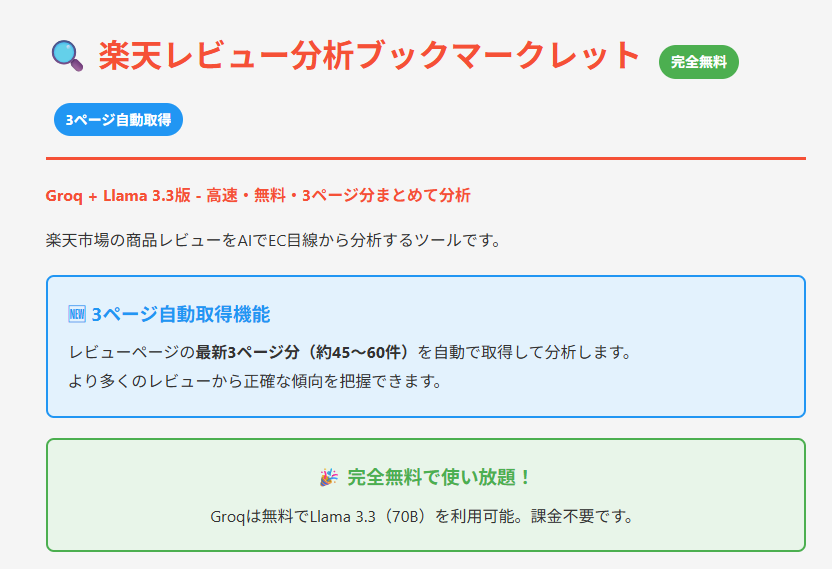営業に依存しないBtoBマーケティング導入のススメ
-
投稿日
-
更新日
- Amazonネットショップコンサル記事
- Yahoo!ショッピングネットショップコンサル記事
- WEB広告運用ノウハウ
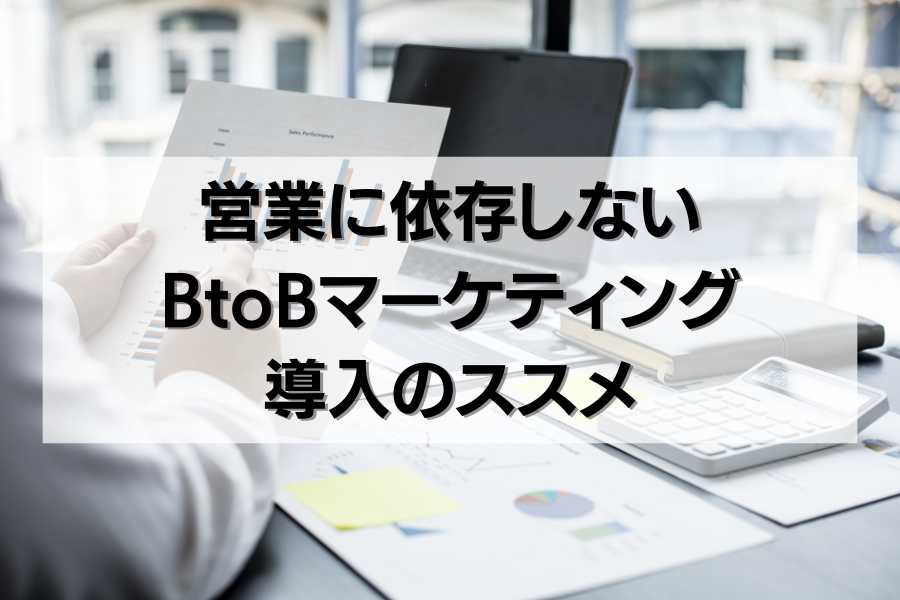
皆様の企業では、営業に依存した経営になっていませんか?
確かに多くの顧客に向けたマーケティングを行うためには潜在層や顕在層に向けた営業を積極的に行う必要性がありますが、必ずしも成功するとは限りません。
逆に営業に依存していると、安定した利益に繋がりにくかったり、営業の効率が悪くなる可能性があったり、個々の能力が活かされなかったりと様々な問題が発生する可能性があります。
そんな状態のままではいずれ問題が浮上してくる可能性があるため、早急に対策する必要性があるでしょう。
そんな時におすすめなのが、営業に依存せずにマーケティングが推進できるBtoBマーケティングです。BtoBマーケティングには様々な手法があり、それぞれ様々なメリットやデメリットがあります。
しかし、そのメリットやデメリットを踏まえたとしても、営業に依存するよりも成果を出せる可能性があるのが大きなポイントです。自社に合ったBtoBマーケティングの手法をチェックし、導入するポイントをしっかり把握することが重要です。
それでは、営業に依存しないBtoBマーケティングとは何か、BtoBマーケティングにおけるそれぞれの手法のメリットやデメリット・注意点、BtoBマーケティングを導入するポイントなどをご説明しましょう。
目次
そもそもBtoBマーケティングとは何?
そもそもBtoBマーケティングとは何か気になる人も多いのではないでしょうか。
BtoBマーケティングとはBisiness to Bisiness、通称BtoBのマーケティングを行うことで、企業が商品やサービスを別の企業に購入してもらい、継続的に関係性を深めることによって自社の売り上げを上げていく方法です。
似たようなマーケティングにBtoCがありますが、こちらはBisiness to Customerと呼びます。BtoCは企業対消費者となるため、商品やサービスの購入者が企業か一般的な消費者であるかどうかの違いがあります。
BtoBマーケティングを行うことによって、相手企業の業務効率化が図れるようになるのが大きなポイントです。もちろん自社企業は相手企業と継続的にコミュニケーションを取ることになるため、日々商品やサービスの向上を目指していかなければなりません。
BtoBマーケティングで大切なのは、課題解決のためのロジックを説明できるか
BtoBマーケティングを推進する上で大事なのは、顧客が抱える課題を解決するためのロジックが説明できるかどうかです。
BtoCマーケティングの場合、一般的な消費者がターゲットになるので、店舗で商品を見た人やサービスを利用した人、広告を見た人などが購入を決めていきます。
しかし、BtoBは消費者ではなく企業が購入者となるため、現場の担当者の一存で商品やサービスの購入には至りません。社内で商品やサービスの購入許可を得なければなりませんし、購入金額も高くなる上、購入が完了するまでの期間も長くなる可能性が高いです。
つまり、購入の意思決定をする人数や購入までの期間、購入目的が大きく違うのがBtoCとの違いです。
BtoBマーケティングは購入を検討している企業にとって重要な工程だからこそ、本当に長い購入期間をかけてまで購入するべき商品やサービスなのか、その商品やサービスを購入すれば本当に現在抱えている課題を解決することができるのかが重要になってきます。
したがって、以下の工程で売れるロジックを構築するのがおすすめです。
- 問題提起
- 原因の深堀り
- 解決策の方向性と求められる結果
- 解決策として紹介できる商品紹介
- 導入を後押しする情報
- 導入に踏み切れる安心感
- 行動の後押し
以上の工程の中で問題提起はキャッチコピーの役割があります。
原因の深堀りは、相手企業が抱えている課題やよくある課題、課題が起きる原因で、解決策の方向性と求められる結果に対し、どんな課題を解決するサービスなのかを説明します。
解決策として紹介できる商品紹介では、課題を解決するサービスがどんな機能を搭載しているのか、どの機能でどんな課題が解決できるのかを説明していくのがポイントです。
さらに導入を後押しするための情報を提供していきます。たとえば、サービスを導入した企業の事例や導入数、シェア数、大手企業の導入事例、メディアに掲載されたことがあるかどうかなどが当てはまるでしょう。
また、導入に踏み切れるための要素として、FAQや導入後のサポート体制、利用したお客様の声などの安心感があるとなお良いです。
後は問い合わせや資料請求、導入相談などの行動を後押しすると売れるロジックが完成します。以上のようなロジックを意識して構築することによって、BtoBマーケティングをスムーズに進めることができるでしょう。
なぜBtoBマーケティングが注目されるようになった?
BtoBマーケティングが注目されるようになった理由は、以下の通りです。
- ユーザーが様々な方法で情報収集ができるようになった
- ユーザーとの関係性を深めることが重要になってきた
- 新型コロナウイルスの影響で営業を初めとする対面業務が難しくなった
これまでBtoBマーケティングはあまり注目されてきませんでしたが、情報収集の幅が格段に広まったこと、これまでのやり方ではユーザーとの関係性を深めることが急務になってきたことなどが、注目される要因になったと言えます。
そもそも新型コロナウイルスの影響によって営業を初めとする対面業務が難しくなった以上、BtoBマーケティングによって営業等に依存しない業務ができるようになるのが大きなポイントです。
それでは、BtoBマーケティングが注目されるようになった理由についてご説明しましょう。
ユーザーが様々な方法で情報収集ができるようになった
BtoBマーケティングが注目されてきている背景には、ユーザーが様々な方法で情報収集できるようになったことが挙げられます。
以前は情報収集の手段が限られていたため、欲しい商品やサービスに関する情報は提供している企業に問い合わせる必要性がありました。しかし、現在ではインターネットの普及により、どの企業がどんな商品やサービスを提供しているのかが個人レベルで調べられるようになっています。
類似商品やサービスがあればそれぞれを比較して検討することもできるようになったため、「この商品やサービスならこの企業」という認識が薄れつつあるのです。
特に企業が商品やサービスの導入を比較検討している場合、BtoCよりも慎重になって決めなければなりません。ここで受け身のままでいると競合他社にユーザーが流れて行ってしまうため、積極的にBtoBマーケティングを行う必要性があります。
いかに顧客の目を引き、検索に引っかかるための工夫を凝らしたマーケティング戦略が立てられるかが重要になるでしょう。
ユーザーとの関係性を深めることが重要になってきた
受け身になって営業を行っていた時代に比べて、現在ではユーザーとの関係性を深めることが重要になっています。
なぜなら、情報収集の多様化や個人レベルで様々な情報の比較検討ができるようになった以上、「いつも使ってるから」「なじみがあるから」などといった理由で商品やサービスを購入するユーザーが少なくなっているからです。
今や現在利用している商品やサービスより、もっと高性能で役に立つものを求めて頻繁に乗り換えが行われているため、営業に頼り切っているようでは、ユーザーが他の商品やサービスに流れやすくなるでしょう。
今まで営業マンが定期的にユーザーの元を訪れて関係性を保っているようなやり方に依存しているのであれば、そんな時代は終わったと言っても過言ではありません。
ユーザーとの関係性をさらに深めるためにも、BtoBマーケティングを推進し、様々なITツールを駆使して商品やサービスを購入してもらったユーザーを自社に繋ぎ止めるための施策を行うことが大切です。
新型コロナウイルスの影響で営業を初めとする対面業務が難しくなった
そもそも現在では新型コロナウイルスの影響によって、営業を初めとする対面業務が難しくなっています。
営業に依存していた企業にとって、個別に営業をかけることが難しくなったのは非常に大きな痛手となるでしょう。
そんな時にこそ、不特定多数のユーザーに対して一気にアプローチがかけられるBtoBマーケティングが注目を浴びています。BtoBマーケティングであれば対面業務をする必要性がなく、社内からオンラインで取引先等と繋がることが可能です。
数回に亘る商談もBtoBマーケティングなら手軽にできるので、対面営業を行うよりも効率良く業務が進められるでしょう。
BtoBマーケティングの方法7選!それぞれの方法のメリットやデメリット・注意点を解説します

BtoBマーケティングの方法は、以下の通りです。
- リスティング広告やディスプレイ広告などのWeb広告を運用する
- オウンドメディア
- TwitterやInstagramなどのSNS運用
- 業界メディアに依頼して掲載してもらう
- 資料請求ポータルサイトに掲載する
- セミナーを開催する
- お問い合わせフォームやSNSを使ってDMを送る
BtoBマーケティングには様々な手法がありますが、それぞれの方法が全ての企業に合っているというわけではありません。必ずしも実践すれば絶対に効果が実感できるというわけではありませんし、何より各企業に合った方法でないと長続きしにくいでしょう。
それぞれどんなメリットやデメリットがあるのかを知ることで、自社企業に合っているのかが判断しやすくなります。
それでは、BtoBマーケティングの7つの方法と、それぞれのメリットやデメリット・注意点についてご説明しましょう。
リスティング広告やディスプレイ広告などのWeb広告を運用する
BtoBマーケティングの一つとして、リスティング広告、ディスプレイ広告、SNS広告などのWeb広告を運用する方法が挙げられます。
リスティング広告とは何らかのキーワードで検索した時の検索結果に掲載される広告であり、検索エンジンを多用しているユーザーが目にしやすい広告です。
ディスプレイ広告とはWebサイトの広告枠に表示される画像や動画のことで、SNS広告はTwitterやInstagramなどのSNS上で配信される広告です。
基本的にWeb広告を運用しても興味がないユーザーにとっては効果がないのではないかと思う人もいるかもしれませんが、それぞれの広告は細かなターゲティングができるのが大きなポイントです。
たとえばリスティング広告であれば検索したキーワードに関連した広告を表示するようになっていますし、ディスプレイ広告なら性別や年齢に関連した広告を表示します。
SNS広告ならフォローしているアカウントの特性や投稿したワードに関連した広告を表示するなら、自社で定めたターゲット層に向けた広告を表示するように設定することで効率良く商品やサービスをアピールすることができます。
Web広告を運用するメリットは、広告費をかけるほど即効性が見込めることです。
検索結果、Webサイト、SNSとほぼ確実にユーザーの目に留まる場所に広告を表示させるので、よりユーザーの目を惹くような広告を発信することができれば費用対効果が高くなるでしょう。
しかし、広告費をかけた分だけスムーズに回収できるかどうかが問題になるため、経験を積み重ねたり広告運用のノウハウがなかったりすると費用ばかりかかってしまうのがデメリットです。
そもそもWeb広告を運用したからといって必ずしも費用対効果が得られるとは限りませんし、何より運用し続けている間は常に広告費がかかります。集客し続けるためにも広告を運用し続けなければならないので、欲しい効果に合わせて予算をコントロールする必要性があるでしょう。
オウンドメディア
オウンドメディアとは、主に企業が運営するブログでユーザーに向けて役に立つ情報を発信する方法です。
いわゆるブログ運営を企業で行うものであり、自社で取り扱う商品やサービスに関連した情報を発信していきます。単なる情報発信だけでなく、見込み客が抱えているであろう悩み事を解決できるような記事を投稿するのも大事な目的です。
企業が公式で情報を発信しているいう信用力を得やすい状態で、一般的なブログ運営よりもユーザーからの信用が得やすく、積極的に情報を発信していけば企業の商品やサービスの認知を大きく広げることができるでしょう。
記事ごとのアクセス数はもちろん、投稿する記事でどんな悩みを解決できるのか、どのようにすれば悩みを解決できるのかゴールを指し示すことを意識することが重要です。
オウンドメディアは企業の商品やサービスの認知拡大と共に、質が高いコンテンツを発信し続けることで検索結果の上位に表示されるようになれば基本無料で多くの集客が見込めるのがメリットです。
もちろんサーバー費用やブログ運用、メディア構築の費用などが発生しますが、集客率を高めるならやっておいて損はないでしょう。
しかし、検索結果の上位に表示されるようにするためのコンテンツ作成には手間と時間がかかるのが大きなデメリットです。
自社企業のみならず、そうそうたる検索結果上位表示サイトが軒を連ねているため、長期的に自社ブログを運営して地道に上位表示を目指す必要性があるでしょう。
ですが、キーワードをずらすことによって検索結果の上位に表示させることは決して難しくありません。効率良く検索結果に上位表示させるためにも、他の企業とバッティングしないキーワードでコンテンツを作成することが重要です。
TwitterやInstagramなどのSNS運用
基本的にBtoCマーケティングで高価を発揮するとされるSNS運用ですが、BtoBマーケティングでも注目を集めている方法です。
TwitterやInstagramなどのSNSを運用することによって、取り扱う商品やサービスなどに対するファンやフォロワーを集めるのが目的です。そしてファンやフォロワーに向けてキャンペーン情報やクーポン情報、新商品や新しいサービスの提供など、役に立つ情報を発信することで集客率を高めることができます。
SNS運用では、いかにファンやフォロワーの関心を惹き、購買意欲を高められるかどうかが重要です。基本的にSNSに投稿できる1回の文字数が少ないからこそ、どうすればユーザーの関心を惹いて購買意欲が高められるかどうか、Webページに誘導できるかどうかが問われます。
とはいえ、SNS運用は見込み客と手軽に繋がれる上に、自社が投稿したユーザーが反応するエンゲージメントの向上が見込める点も見逃せません。ユーザーが多く反応してくれるほど商品やサービスの購入や利用に結び付く可能性が高いため、SNS運用は非常に有用なBtoBマーケティングになるのがメリットです。
SNS運用はBtoCマーケティングで主流になっている方法ではありますが、BtoBマーケティングの観点で見るとSNS運用をしている企業が少ない傾向にあります。つまり、SNS運用における競合が少ないため、いち早くSNS運用を始めることで高い集客率が見込める可能性があるでしょう。
しかし、成果が見込めるSNS運用を行うためには、実際にユーザーの関心が惹ける投稿ができるかどうかが最重要です。各企業にとって魅力的な投稿ができるかどうかノウハウが必要ですし、継続して運用するための手間や時間がかかるのもデメリットです。
業界メディアに依頼して掲載してもらう
業界メディアへの掲載とは、自社が属している業界に特化したメディアに、自社の記事広告やバナー広告の掲載を依頼するというものです。
業界メディアに自社で取り扱う商品やサービスを広告にしてアピールすることで、将来的に顧客になる可能性がある企業に対して効率良く認知が広げられるのがメリットです。
もちろん業界メディアによっては期間契約型、インプレッション課金型、PV保証型といった様々な料金体系があるので、その中から自社の予算に応じた料金体系を選ぶことになります。
しかし、業界メディアに掲載を依頼するにあたって注意したいのが、ビジネスモデルによってROASが合わない可能性があることです。
ROASとはReturn On Advertising Spendのことで、広告の費用対効果という意味があります。つまり、広告費に対してどれだけ売上が出せたのかが重要になってきますが、ビジネスモデルによっては広告費に対する費用対効果が見込めない可能性があるでしょう。
したがって、ビジネスモデルとROASを合わせる工夫が必要です。
資料請求ポータルサイトに掲載する
資料請求ポータルサイトとは、様々な情報が1ヶ所にまとめられたWebサイトのことで、様々な商品やサービスを比較した上で興味がある資料を一括請求できます。
競合他社が既に掲載している中で自社の商品やサービスの資料を掲載することになりますが、商品やサービスの導入を検討している段階の見込み客が数多く存在しているのがメリットです。
既に検討している企業が商品やサービスの資料請求を行う可能性が高いため、見込み度が高いリードを獲得できるでしょう。業界メディアや自社ブログメディアなどと違い、資料請求ポータルサイトは成功報酬型が一般的なので毎月費用が発生するわけではないのもポイントです。
しかし、資料請求ポータルサイトに掲載する以上、資料請求された時のスピード感が非常に重要になるので注意しましょう。
資料請求する企業は、自社以外にも他社で気になる商品やサービスの資料を請求している可能性があるので、あまりもたもたしていると競合他社に流れてしまう可能性があります。
もしも資料請求が行われた場合はすぐに電話をかけて、競合他社よりも素早くアプローチをかけることが大切です。
セミナーを開催する
セミナーを開催して自社の商品やサービスについて、より深く知ってもらう方法もあります。
既に自社と接点がある見込み客に対して招待メールを送ったり、何らかのキーワードで検索したユーザーや各種広告を見て興味を持ってくれたユーザーをセミナーに招待したりするのが一般的です。
場合によっては無料セミナー小口サイトにセミナー情報を掲載して参加者を募集する必要性もあるでしょう。
セミナーを開催する場合は、アピールする商品やサービスに関してどんなことを説明するのか、どのターゲット層に向けた内容にするのかなどを決める必要性があります。
特にBtoBマーケティングにおいては様々な課題や悩みを持つ企業を中心に参加してくる以上、商品やサービスの魅力を伝えて課題解決や悩みの解消に繋がるようなプレゼンができるようにならなければならないでしょう。
上手くいけば見込み客の検討度合いが引き上げられるだけでなく、より商品やサービスに関する強い印象が与えられるのが大きなメリットです。特に見込み客との対面によって直接コミュニケーションが取れるのはもちろん、信頼関係も構築できるので高い成果に繋がりやすいでしょう。
しかし、新型コロナウイルスの影響下でセミナーを開催するのは容易なことではありませんし、会場やスタッフの手配などセミナー開催の事前準備だけでかなりの労力や時間を要するのがデメリットです。
セミナーを開催したところで必ずしも成果に繋がるとは限らない以上、安易にセミナーを開催しようとするのはおすすめできません。
ですが、セミナーのデメリットがない方法として挙げられるのが、オンラインでセミナーを行うウェビナーです。
ウェビナーであれば会場やスタッフの手配も用意する必要性がなく、見込み客に手軽に傘下を促すことができます。オンライン環境を整える必要性があるものの、新型コロナウイルスの影響を受けることなく商品やサービスのアピールができるのがポイントです。
お問い合わせフォームやSNSを使ってDMを送る
自社の商品やサービスを効率良く直接的にアピールしていきたいなら、同じ業界の企業のお問い合わせフォームやSNSを使ってDMを送る方法があります。
明確に商品やサービスをアピールするターゲット層が分かっているのであれば、見込み客になり得る企業のお問い合わせフォームやSNSを使ってDMを送るのが効果的です。
ダイレクトに商品やサービスを知ってもらえる上に認知度も高まるのが大きなメリットですが、同時に顧客にとって迷惑なDMになる可能性があるのもデメリットです。
BtoBマーケティングを導入する時のポイント

BtoBマーケティングを導入する時のポイントは、以下の通りです。
- 顧客のニーズや課題を理解する
- 社内部署同士の連携を強化する
- マーケティングの目的をハッキリさせる
- ITツールの導入
- 施策を定期的に見直す
BtoBマーケティングは単に導入すればいいというものではなく、何を目的に導入するかがポイントです。
それでは、BtoBマーケティングを導入する時のポイントについてご説明しましょう。
顧客のニーズや課題を理解する
BtoBマーケティングを導入する上で何よりも重要なのは、顧客のニーズや課題を理解することです。
BtoCマーケティングなら顧客が欲しいものを購入するのに対し、BtoBマーケティングは顧客が抱えている課題や悩みを解決するために必要なものを導入したいと考えています。
このことから、顧客にとって課題や悩みを解決できないような商品やサービスを勧められても時間の無駄ということになりかねません。
したがって、自社の商品やサービスを導入することでどんな課題を解決し、悩みが解消できるのかを把握した上で顧客にアプローチをかけることが大切です。BtoBマーケティングを導入する際は、顧客のターゲット層を絞り込み、自社の商品やサービスがどのように役立てられるのかを理論的に説明できるようにしておきましょう。
もちろん業種や立場によって抱えている課題が違う上に、自社以外にも競合他社と商品やサービスを比較している可能性が高いため、競合他社にはないメリットも合わせて説明できるとなお良いでしょう。
社内部署同士の連携を強化する
これから初めてBtoBマーケティングを導入する場合、新たにマーケティング部門を設立して一任させるケースが多いのではないでしょうか。
しかし、BtoBマーケティングにおいて重要なのは、社内部署同士の連携です。つまり、BtoBマーケティングはマーケティング部門だけが努力しても達成できるものではなく、他の部門と連携していく必要性があります。
営業部門やカスタマーサポート部門、商品開発部門など、アピールする商品やサービスによって連携する部門も変わるでしょう。
マーケティングの目的をハッキリさせる
上記でご説明したように、BtoBマーケティングの手法には様々な種類があるので、それぞれのマーケティングの目的をハッキリさせることが大切です。
オウンドメディアならブログにアクセスしたユーザーに向けて有益な情報を発信したり、SNS運用なら短い文章でファンやフォロワーに向けてアピールしたりと、マーケティングの手法によって目的は大きく違います。
自社が求める成果を実現させるにはコストをかける必要性があるものの、自社に合わないマーケティング手法に大量のコストを投じてもまとまった成果には繋がらない可能性が高いです。
BtoBマーケティングにおいて絶対に避けたいのは、大した成果も出せずにリソースばかりを消費していくような事態です。これを避けるためにも、BtoBマーケティングの目的をハッキリさせた上でマーケティングの方法を選びましょう。
ITツールの導入
BtoBマーケティングを導入する時は、業務効率化のためにITツールを導入する必要性があります。
なぜなら、BtoBマーケティングにおいて人の手で行う作業量が膨大すぎるからです。大量のリード情報を手分けして精査し、それぞれに適切な対応を行ったり、様々なデジタル施策を行ったり、社内部署同士で情報共有を密に行って行動な情報交換をした上で次に必要な施策を考えたりと、複雑かつ膨大な作業量が発生します。
これを全て人の手のみで行うのは現実的ではないため、各種業務を簡略化し、効率良くできるようにするためのITツールを導入する必要性があるでしょう。
ITツールにも様々な種類がありますが、基本的に人の手で行わなくても良い作業を自動化したり、業務効率化が図れたりと様々なメリットがあります。ただ、施策内容や予算、コスト、共有する社員数など様々な要素によって導入するITツールも変わってくるでしょう。
したがって、採用するマーケティングの方法など様々な状況に合わせて導入するITツールを選ぶことが大切です。
施策を定期的に見直す
次に意識したいのは、ずっと同じ施策のままBtoBマーケティングを進めるのではなく、定期的に施策を見直すことです。
マーケティング戦略において常に意識したいのは、常に新しい技術やサービスが開発されていること、年々複雑化する業態に対応していく体制、顧客のニーズの急速な変化を把握すること、そして今まで競合じゃなかった企業が競合になることです。
競合が増えるということは顧客がそちらに流れる可能性がある他、顧客のニーズの変化によって自社の商品やサービスが利用されなくなってしまう恐れがあるでしょう。
長くBtoBマーケティングを推進するためにも、定期的に市場調査を行い、今の施策に問題がないか、このままでは自社の強みが薄れないか確認・修正・改善することが重要です。
BtoBマーケティングを外注するのもアリ?

確かに自社でBtoBマーケティングを導入することで営業に依存することなく商品やサービスのアピールができますが、BtoBマーケティングを導入するのは簡単にできることではありません。
マーケティングの戦略策定・実行、どんなマーケティングの方法を採用するのか、どのくらいのコストがかかるのかなど、成果が出るまで施策を実行しなければならない以上、時間や手間、コストがかかりすぎてしまいます。
自社でやれることから始めようと思っていても、情報収集や戦略設計の工数にかなりの時間がかかってしまうのが難点です。BtoCであればそこまで時間はかかりませんが、BtoBの場合は企業が顧客となるため、購入を検討する期間が長く、意思決定に多くの人数が関係します。
しかも本業と兼任する場合は本業を疎かにすることなく両立させなければなりませんが、上手くリソースを割いていかないと計画倒れになりかねません。
このことから、BtoBマーケティングの導入を検討する段階で止まっている企業も少なくないでしょう。そんな時におすすめなのが、BtoBマーケティングの外注です。
BtoBマーケティングを外注することで人材やリソースを割くことなく、経験豊富な企業に任せられるので、自社でBtoBマーケティングを導入しなくても効率良く推進できます。
BtoBマーケティングを外注するメリット
BtoBマーケティングを外注するメリットは、以下の通りです。
- 豊富なBtoBマーケティングの知識や経験、ノウハウを持った状態で推進できる
- BtoBマーケティングを客観的な視点で進められる
- BtoBマーケティングのノウハウが吸収できる
- 社内のリソースが軽減される
それでは、BtoBマーケティングを外注するメリットについてご説明しましょう。
豊富なBtoBマーケティングの知識や経験、ノウハウを持った状態で推進できる
BtoBマーケティングを外注する最大のメリットは、豊富なBtoBマーケティングの知識や経験、ノウハウを持った状態で推進できることです。
自社でBtoBマーケティングを導入する場合、情報収集や戦略設計はもちろん、マーケティングプロセスの全体像を把握するだけでも時間がかかってしまいます。他の業務と兼任している場合は本業を疎かにせずにBtoBマーケティングを行わなければならないことを考えると、非常にハードルが高いでしょう。
しかし、最初からBtoBマーケティングの経験やスキル、ノウハウが豊富にある企業に外注することで、これらの問題が解消されるのが大きなポイントです。
新たに人材を登用する必要性がなく、自社でBtoBマーケティングを行う時間も手間もコストもかかりません。自社に余裕がない時ほど外注するのがおすすめです。
BtoBマーケティングを客観的な視点で進められる
BtoBマーケティングを外注することによって、客観的な視点でBtoBマーケティングが進められるのがメリットです。
本来であれば少しずつでも自社でBtoBマーケティングを推進するのがベストなのかもしれませんが、漠然としたマーケティング計画では成果を出すことはできないでしょう。
したがって、ビジネスゴールを定量的に示した指標と共に各プロセスにおける中間目標の達成度などを考慮してマーケティング計画を立てる必要性があります。
とはいえ、初めてBtoBマーケティングを導入する企業の場合。マーケティング計画を立てるのに必要な経験やスキル、ノウハウがなく、実績や蓄積されたデータもない状態から始めなければなりません。
しかし、豊富な実績を持つ外注先であれば似たような業務のBtoBマーケティングを推進した経験やマーケティングフェーズにおけるデータを保有しているのが大きなポイントです。
このことから、BtoBマーケティングを外注することで客観的にマーケティング計画を進めることができます。
BtoBマーケティングのノウハウが吸収できる
BtoBマーケティングを外注することによって、BtoBマーケティングのノウハウが自社で吸収できるのが大きなメリットです。
BtoBマーケティングを外注する時に気を付けたいのは、外注費用が発生することです。BtoBマーケティングを外注し続けることで外注費用が発生し続けますが、プロのマーケティング制作の技術や知識、ノウハウを吸収することで、やがて自社内で独自のBtoBマーケティングを推進することができるようになります。
一口にBtoBマーケティングといっても作業量は膨大ですが、基本的に以下のような流れで進めていきます。
- 企画
- 設計
- 構成
- 制作
- 公開
- 分析
以上の流れでマーケティングを進めていきます。
もちろん採用したマーケティングの方法によって作業工程は変わっていきますが、どのようにすればBtoBマーケティングが進められるのかが間近で分かるのがポイントです。
社内のリソースが軽減される
BtoBマーケティングの外注は社内のリソースを軽減することにも繋がります。
というのも、新たにBtoBマーケティングを導入して推進する場合、多くの人材を確保しなければなりません。たとえば、一般的に以下のような人材を登用する必要性があります。
- マーケティング責任者
- 企画・改善のプランナー
- 広告運用の運用実務担当者
- 企画・改善のディレクター
- サイト・MA運用の運用実務担当者
- コンテンツ制作担当者
- デザイナー
- コーダー
- プログラマー
以上の人材の他にも関係部署との連携も必要になるため、全体的に発生するリソースは膨大になるでしょう。さらに大変なのは、以上のような技術やスキルに精通している人材が少ないため、人材を探すだけでも時間がかかる上に、別途で採用費用も発生することです。
離職されるリスクも考えると、自社でBtoBマーケティングを導入するのは膨大なリソースが発生すると言えます。
しかし、BtoBマーケティングを外注することで以上のような問題を考える必要性がないため、大幅なリソース削減が実現できます。
将来的に自社でBtoBマーケティングの導入を検討しているのであれば、BtoBマーケティングが推進できるまでの準備期間として外注することによってノウハウを吸収しつつリソースを活用してからの方が費用対効果が高くなりやすいでしょう。
BtoBマーケティングを外注するデメリット
BtoBマーケティングを外注するデメリットは、以下の通りです。
- 外注先の会社が業界の知識や自社企業の商材を理解するのに時間がかかる
- 依存度が高いほど社内にBtoBマーケティングのノウハウが蓄積されない
それでは、BtoBマーケティングを外注するデメリットについてご説明しましょう。
外注先の会社が業界の知識や自社企業の商材を理解するのに時間がかかる
BtoBマーケティングを外注するにあたって気を付けておきたいのは、外注先の会社が業界の知識や、自社企業の商品やサービスの商材を理解するのに時間がかかってしまうことです。
基本的にBtoBマーケティングを効率良く推進するには自社が取り扱う商品やサービスといった商材を理解しなければなりませんし、その業界の知識も必要です。
業界や商材を理解するために入念なコミュニケーションを重ねたにもかかわらず、最終的に出来上がったものは自社で想定していたものと違っていたということもあります。この場合、もう一度修正してもらうか、自社内で直す工程が発生してしまうでしょう。
したがって、事前準備として外注先との話し合いを重ねて業界や自社の商品やサービスについて理解してもらう必要性があります。
また、最終的な成果物が想定していたものと違っていた事態を可能な限り避けるために、外注先の実績を確認して類似した業態のマーケティングを請け負った実績があるかどうか確認しましょう。
依存度が高いほど社内にBtoBマーケティングのノウハウが蓄積されない
将来的に自社でBtoBマーケティングを推進するのであれば、外注先におけるBtoBマーケティングの技術やスキル、ノウハウを吸収する必要性があります。
しかし、ノウハウが吸収できるかどうかは外注先への依存度によって左右されるでしょう。
もしも外注先に任せっきりにしている依存度が高い状態だった場合、自社内でのノウハウが蓄積されにくくなってしまいます。業務の工数が減る一方で外注費用は発生し続けるため、将来的に外注費用を発生させないようにノウハウを吸収する体制を構築する必要性があるでしょう。
BtoBマーケティングの外注先の選び方と注意点
BtoBマーケティングの外注先の選び方と注意点は、以下の通りです。
- BtoBマーケティングをする目的と課題をハッキリさせる
- ハッキリさせた目的と課題に合った外注先を探す
- 外注先による費用とサービス内容を比較する
それでは、BtoBマーケティングの外注先の選び方と注意点についてご説明しましょう。
BtoBマーケティングをする目的と課題をハッキリさせる
最初にBtoBマーケティングをする目的と課題をハッキリさせましょう。
BtoBマーケティングにおいて、ビジネスゴールを定量的に示した指標と共に各プロセスにおける中間目標の達成度などを考慮してマーケティング計画を立てる必要性があります。
しかし、それらが決まっていない状態で外注先を選ぼうとしても、外注会社の支援内容が目的と噛み合っていない可能性があります。自社で決めた目的や課題によって行う施策に応じて、どんなプロセスが必要になるのか、どんな外注先に依頼すれば効率良くマーケティングが推進できるのかをハッキリさせることが大切です。
ハッキリさせた目的と課題に合った外注先を探す
上記の工程で目的と課題をハッキリさせたら、その目的と課題に合った外注先を探しましょう。
目的と課題から見える自社に足りない要素が分かってくるので、その要素を補ってくれる外注先を探すのがポイントです。主な外注先は、以下の4社です。
- コンサルティング会社
- BPOサービス会社
- 人材シェアリング会社
- ツール会社
コンサルティング会社は戦略や施策の企画立案や設計支援に強いため、目標達成のための戦略設計を外注したい時におすすめです。
BPOサービス会社は施策の設計から実行業務までを中心に行うので、与件に合った納品成果物や実行業務を外注したい時におすすめです。
人材シェアリング会社はクライアント企業が必要とする知見やスキルを持つ人材を業務時間単位で提供するため、与件に合った人材と業務時間を確保したい時におすすめです。
ツール会社は分析・開発ツールなどの開発や提供を行うので、ツールで提供できる機能やデータが不足している時におすすめです。
外注先による費用とサービス内容を比較する
自社に足りない要素を補ってくれる外注先の種類が分かったら、複数の外注先に依頼する時に発生する費用とサービス内容を比較しましょう。
外注先によってサービス内容に大きな違いがあるため、費用が安いと思っていたら思ったほどサービス範囲が狭いことも少なくありません。
費用の安さだけで比較するのではなく、サービス内容が充実しているかどうかを確認して決めることが大切です。
まとめ

営業に依存しないBtoBマーケティングは、将来的な業務効率化や新型コロナウイルスの影響なども考えると、今後検討する必要性があるでしょう。
BtoBマーケティングを導入することでマーケティングの業務効率化が実現できるだけでなく、様々な方法で商品やサービスがアピールできるようになるなど様々なメリットがあります。
もちろんデメリットや注意点もあるので、外注も含めてBtoBマーケティングの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
▼参考 btobに強いテレアポ代行|費用相場と選び方について詳しく解説 - セールスブレイン株式会社
無料でEC運営・WEBマーケティング
のノウハウをお話しています
WEB集客やネットショップ運営などでお悩みがあれば一度ご相談ください。ご相談は無料で行なっております。
通販お役立ち資料無料ダウンロード
この記事を書いた人
株式会社ALL WEB CONSULTING
代表取締役
江守 義樹(えもり よしき)
WEB解析士協会 上級WEB解析士
ネットショップ店長として0ベースからショップ運営を行い約1年で月商1,000万規模のショップに育成。
その後、ECサイト専門のコンサルティング会社に勤務し、月商数億規模のサイトから立ち上げたばかりの小規模なサイトまで数百社のECサイトのサポートを行う。
2018年に前身であるLOCUSコンサルティングを創業。
2020年ECサイト・ネットショップ支援に特化した株式会社ALL WEB CONSULTINGを創業し代表取締役に就任。
データアナリストとしてサイト解析を軸にした戦略的なSEO対策、サイト制作、WEBプロモーション、などEC支援全般のスペシャリストとして活動中。





 03-6276-8654
03-6276-8654





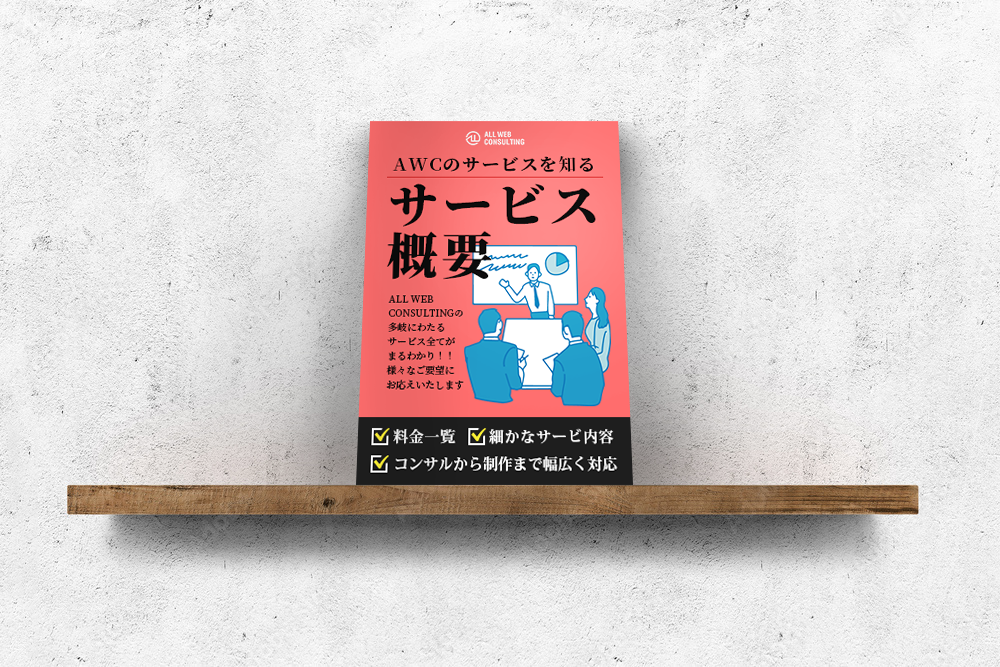
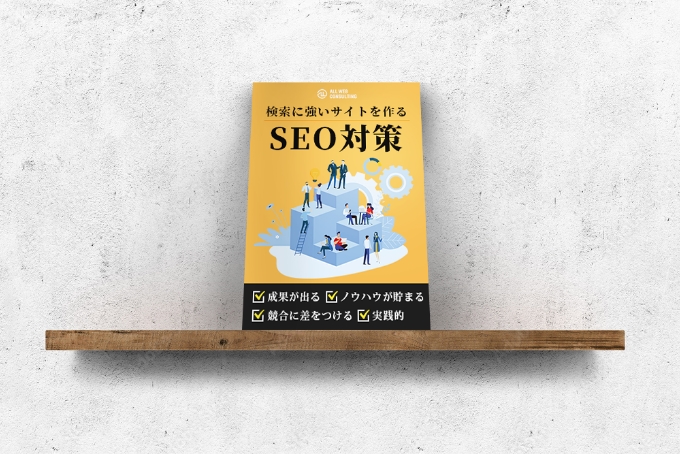
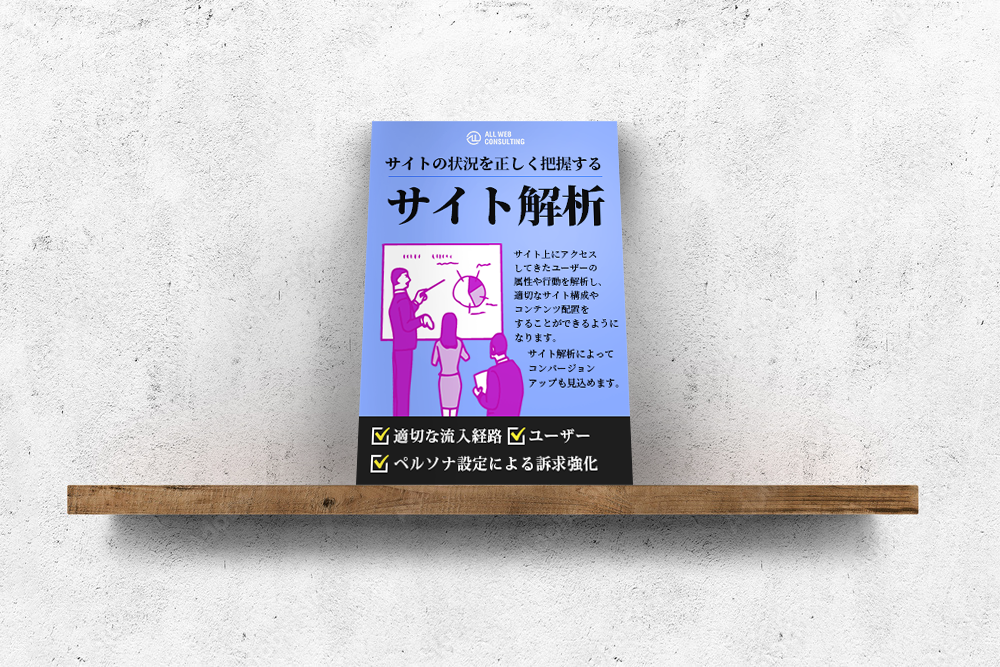
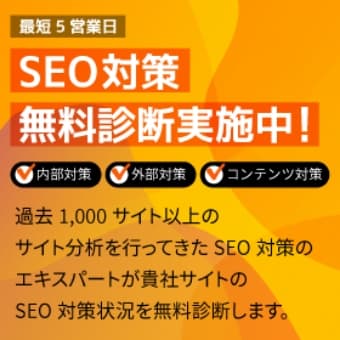
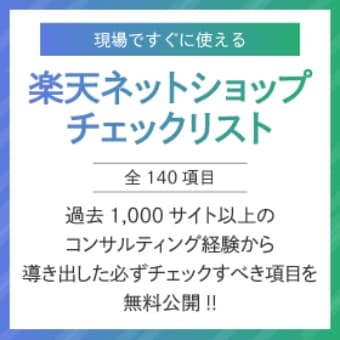
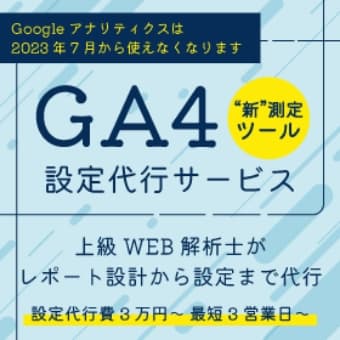




 カテゴリー
カテゴリー